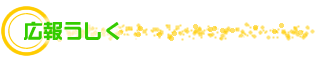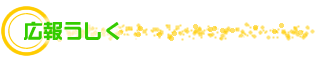 |
|
作成日:2007/02/27
|
|
|

|
ご存じですか? 里親制度
|
|
|
里親制度は、さまざまな事情により家庭での養育を受けることができないお子さんを、里親の家庭で、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で養育していただく子どもの福祉のための制度です。茨城県では、子どもたちの健やかな成長のために、里親になっていただける方を広く募集しています。
|
|
|
▼里親には次の種類があります
|
|
|
○養育里親
|
|
|
子どもが家庭に戻れるまで、または自立できるまで(満18歳になるまで)家庭で養育する里親のことです。
|
|
|
○短期里親
|
|
|
1年以内の期間を定めて子どもを家庭で養育する里親のことです。
|
|
|
○親族里親
|
|
|
両親による養育が期待できない子どもを家庭で養育する、その子どもの三親等以内の親族の里親のことです。
|
|
|
○専門里親
|
|
|
2年以内の期間を定めて、児童虐待などの影響を受けた子どもを養育する里親のことです。
|
|
|
○職業指導里親
|
|
|
子どもの自立を支援することを目的として、職業の基礎的な能力や自活していくうえで必要な態度やルールを身に付けさせる里親のことです。
|
|
|
▼里親になるには
|
|
|
里親になるためには、里親とその家族が子どもの養育について理解と情熱を持ち、健全な家庭生活を営んでいることなどいくつかの条件があります。
|
|
|
▼子どもの養育について
|
|
|
預かった子どもの養育は、基本的に実子と同じ気持ちで育てますが、特に次の点に留意する必要があります。
・家庭は常に和やかにし、子どもの心身を害する言動は避けましょう。
・子どもの栄養、発育など健康面に十分注意し、異常があるときは直ちに医療機関に受診させるなど適切な措置をとりましょう。
・子どもの福祉を図る上で好ましくない用務に従事させたり、虐待したり、酷使したりしてはいけません。
※養育方法などについての研修や相談は、児童相談所で行います。
|
|
|
▼養育の費用について
|
|
|
子どもの養育を里親にお願いする場合には、その養育に要する費用(里親手当、一般生活費、教育費、学校給食費、医療費、賠償責任保険など)を県が負担します。
|
|
|
▼申し込み方法
|
|
|
里親になることを希望される方は下記までご相談ください。県は家庭調査などを実施し、社会福祉審議会の意見を聞いた上で、適当と認めた方を里親として認定し、里親として登録します。
|
|
|
▼養子縁組との関係について
|
|
|
家庭に戻れる見込みがない子どもとの養子縁組を希望し、養子縁組が成立するまでの間、養育里親になることも可能です。養子縁組には次の2種類があります。
○普通養子縁組
年長者、尊属以外の方を養子とすることができます。実親との親子関係は残ります。
○特別養子縁組
原則として6歳未満の子どもで、実親による監護が著しく困難な場合など、子どもの福祉のために必要であると家庭裁判所が認めた場合に成立します。実親との親子関係は解消され、また、原則として離縁はできません。
|
|
|
▼里親会について
|
|
|
茨城県には、里親として登録された方がお互いに意見を交換したり、研修したりするための自主的な組織として、8つの「地区里親会」があります。県社会福祉協議会内には「茨城県里親連合会」が結成されています。
|
|
|
☆里子のいる家庭から
|
13年ほど前、児童相談所から生後6カ月の赤ちゃんを預かりました。児童相談所に里親登録を済ませてから3カ月後のことです。現在は4人の里子とともに暮らしています。さまざまな理由で児童相談所に保護された18歳までの子どもの多くは、児童福祉法に基づき乳児院や児童養護施設に預けられます。子どもたちの中には集団の中での養育にはなじみにくく、きめ細かな養育環境が必要な子どもたちがいます。里親はそのような子どもたちを家庭的環境の中で養育するという大きな社会的な役割があります。
今、里親が足りません。里子を育てている里親の活動もあまり知られてはいません。家庭に恵まれない子どもたちが出会いに胸をふくらませています。ぜひ里親に登録して、子どもたちと共に歩んでみませんか。
|
|
|
|
|
|
問い合わせ
茨城県土浦児童相談所 電話 821-4595
市児童福祉課 電話 873-2111 内線 1734(家庭児童相談室) 
|
|
|
|
|
トップページ → p1・p2・p3・p4・p5・p6・p7・p8・p9・p10・p11・p12・p13・p14・p15・p16・p17・p18 |