2-A 緑地回復 (2024年5月7日更新)
緑化計画の立て方
II-A 緑地の回復基準(基準緑化面積)
開発により失われた緑地の回復や住宅の緑化を進めるために、以下の基準緑化面積以上の緑地面積を得られるよう、緑化計画を立ててください。
実際の使用面積が、500m2以下であっても、開発に関わる筆地の総面積が500m2以上であれば緑化計画対象事業となります。
|
基準緑化面積の算出方法 基準緑化面積は、以下の式により算出して下さい。 ( 基準緑化面積 )=( 空地面積1-控除面積2 )× 緑化率3
※1 空地面積の算出方法は下記を参照下さい。
※2 控除面積とは、道路・公園・公共緑地・その他公衆の用に供する敷地で、市に帰属する用地の合計面積とします。
|
【※1空地面積の求め方】
( 空地面積 )=( 敷地面積4 )×(100-建蔽率5 )×1/100
※4 敷地面積は、開発全体の総面積とします。面積は、筆地の面積で算出し、筆地の一 部でも敷地にかかっていれば筆地の全面積が敷地面積に含まれると考えます。
※5 建蔽率は、各用途地域の法定建蔽率とし、市街化調整区域は第一種住居地域に準じ、60%とします。
【※3緑化率】
緑化率は、下表の通りとします。
| 空地面積 | 緑化率 | |
|---|---|---|
|
戸建住宅を目的に する面的開発 |
その他 | |
| 500m2未満 | 2.5/10 | 1.5/10 |
| 500m2以上1,000m2未満 | 3/10 | 2/10 |
| 1,000m2以上3,000m2未満 | 4/10 | 2.5/10 |
| 3,000m2以上5,000m2未満 | 5/10 | 3/10 |
| 5,000m2以上20,000m2未満 | 6/10 | 3.5/10 |
| 20,000m2以上 | 別途協議 | |
緑化面積の算出
緑地面積は、平面状に緑地を確保し面積を算出する以外に、次の算出基準により立体的な緑を面積に換算して算出することもできます。
表)緑地面積の算出基準
|
種別
|
算出方法
|
備考
|
|
|---|---|---|---|
| 既存樹木 |
・樹冠の投影面積 ・集団の場合は、外側の樹木の樹冠を直線で結んだ線で囲まれた面積 |
||
| 植栽樹木 |
高木 |
1本当り 10m2 |
成木に達した時5m以上 植栽時に3m以上 |
| 中木 | 1本当り 3m2 |
成木に達した時3m以上 植栽時に1m以上 |
|
| 低木 | 地表をおおった面積 | 1m2当り5株以上植栽すること | |
| 地被植物 | 地表をおおった面積 | ||
| 生垣 | (延長)×0.5m | ||
-計算例- 〔敷地面積2,025m2の店舗。用途地域は第一種住居地域。〕
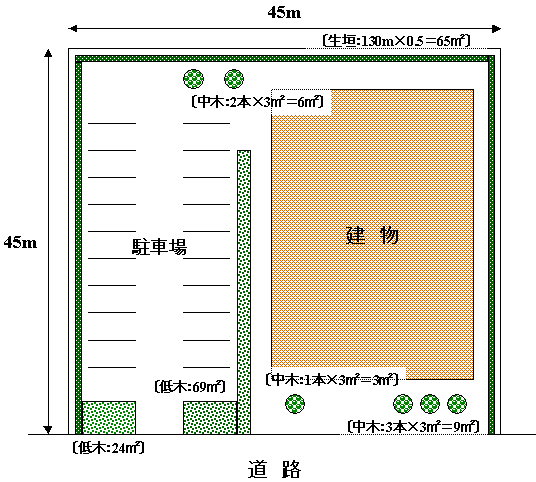
【基準緑化面積】
空地面積)= 2,025 × (100 - 60 ) × 1/100 = 810(m2)
敷地面積 建蔽率
∴(基準緑化面積)= ( 810 - 0 ) × 2/10 = 162(m2)
上で求めた空地面積 控除面積 緑化率※
※緑化率:この例の場合は、「空地面積500m2以上1,000m2未満」・「その他」を適用
【緑化面積】
(中木)= 6本×3m2 = 18m2
(低木)= 24m2+69m2= 93m2
(生垣)= (44.5+45+44.5)m×0.5m = 67m2
∴(緑化面積)= 18+93+67 = 178m2
! ( 基準緑化面積 162m2 ) ≦ ( 緑化面積 178m2 )
緑地回復の基本的な考え方
1. 現存する植生と樹木の保存を考えてください。
2. みどりの量感を高めるため、生垣などの接道面緑化を実施してください。
3. 高木を植える場合は、牛久市の潜在自然植生を考え、樹種を選定してください。
(スダジイ・ケヤキ・シラカシ・コナラ・クヌギ等)
4. 空地のある場合は、できるだけ低木・地被植物などで緑化してください。
みどりと自然のまちづくり条例topへ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課です。
分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線2521~2524) ファックス番号:029-871-1956
メールでのお問い合わせはこちら